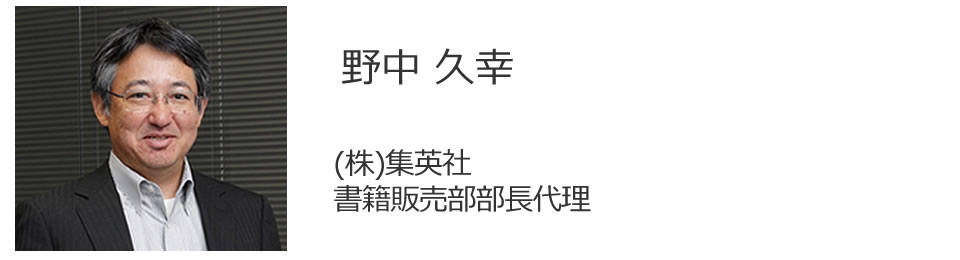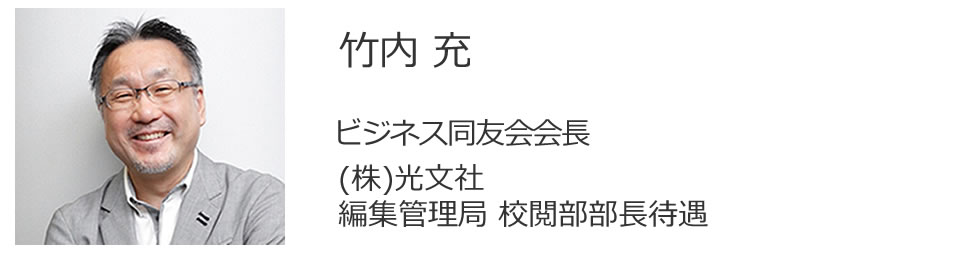— お2人は1980年に新設された情報学部の一期生とのことですが、学生時代から親しかったんですか?
竹内 なにしろ学科生が50人足らずしかいないので、自ずと仲良くなりましたね。雀友というか(笑)。
— 初代の情報学部にはどんな学生が集まっていたんですか?
竹内 日本初の情報学部というふれこみだったんですが、情報とはいっても、僕らは広報学科なので、漠然とマスコミ志望の学生が多かったと思います。テレビや出版に対して憧れを抱くような可愛らしい10代の若者(笑)が集まっていたという感じで、僕もその1人でした。
野中 将来、編集者をやってみたいという気持ちはありましたが、具体的にどこに行って何をやるのかというビジョンはなかったと思います。本当に漠然とした夢でしたね。
竹内 それほど就職を意識してここを選んだという感じではなかったんですが、僕個人としては、新設時の教授のラインナップに惹かれました。つい最近までテレビ、新聞、出版などのマスコミ各社でバリバリに活躍されていた方たちが、他の学校を経由せず、現役の雰囲気のまま教鞭をとることに大きな魅力を感じたんです。
野中 そういう意味では、私にとっては学長の小尾乕雄先生の存在が大きかった。私は東京の都立校に通っていたんですが、小尾先生は都立高の群制度をつくられた方で、そういう方が教えておられるのかと思い、少なからず縁も感じました。
— 当時の情報学部はどんな雰囲気だったのでしょうか?
竹内 文教大学は教育学部がメインですから、当時はこの学部が出来たことすら知らない学生もいたかもしれません(笑)。キャンパスの端の離れ小島みたいな所でひっそりと活動しているようなイメージでしょうか。でも、僕はそれがかえって良かったと思う。まるで合宿所か塾のような雰囲気がありました。
野中 学生数も少ないし、場所(越谷キャンパス)も田舎でしたから、下宿率がとても高かったのを覚えていますね。
竹内 でも、君は都心に実家があるのに、北千住で一人暮らししてたじゃない。
野中 まあ、そうだけど(笑)。東京都に居ないとね。
竹内 僕も新潟から上京したので、妙なこだわりでどうしても埼玉じゃなくて東京に住みたかった。だから、東京のギリギリ端の足立区竹ノ塚に住んで、そこを拠点に映画を観に行ったりしたいと思っていました。
— お2人で遊びに行くこともあったんですか?
野中 2人きりはなかったんじゃないかな。僕は1年生の時は野球をやっていたので、広報学科で同じように野球をやっている友だちとはよく一緒だったんですけど、他の人とはあまり遊んでいなかった。2人が仲よくなったのは2年目以降ですね。
— 何かきっかけがあったんですか?
竹内 それは麻雀でしょう(笑)。
野中 あの頃は大学の近くに下宿している人の部屋に集まってはしょっちゅう麻雀をやってましたね。
— 80年代初めの東京は地方から上京した竹内さんにとって、カルチャーとしても刺激的だったんじゃないですか。
竹内 そうですね。最近、当時の大学ノートを引っ張り出したら、映画やテレビ、本などについて、かなりきっちりとした評論のようなものが書いてありました。いろんなものを吸収しようというストイックな学生だったんだなと自分でもちょっとびっくりしましたね。
野中 今の話を聞くと、私は竹内みたいにまじめじゃなかったかもしれません。高校時代は甲子園を目指して野球に打ち込んでいたので、いちばん本を読んだのは中学時代でしょうか。

黄金期に飛び込んだ出版の世界
— お2人とも、84年に出版社に就職されますが、マスコミの中でも、なぜ出版社だったのでしょうか?
野中 テレビ局は倍率が高かったし、もちろん出版社も大手は狭き門で、どこに入れるという確証はなかったんですが、運良くうちの会社に決まったという感じですね。今は私も面接官をやりますが、目の前の学生がどこの大学なのか全く分からずに面接します。そういう意味ではラッキーだったのかもしれません。
竹内 僕は報道の仕事がしたいと思っていたんです。現場で取材をする仕事が出来れば媒体は何でも良かった。とはいえ、野中の言うように、テレビ局や新聞社には力及ばず入れませんでした。ちょうど光文社が『週刊宝石』を創刊した時で、この雑誌が他のおじさん向けの週刊誌と比べて非常に魅力的に映ったんです。「そうか、雑誌のジャーナリズムというのもあるな」ということに気づいて入社試験を受けました。大手出版社を受けたのは一社だけです。脇目も振らずに「この『週刊宝石』がつくりたい」と。
採用試験で覚えているのは、僕個人のデータよりも文教大学についての資料のほうが多かったことですね。というのも、これまでマスコミ系を志望する学部がなかったので、卒業生もいない。「文教大学って何?」から説明しなければならないわけです。もっとも、卒業生がいなかった分、色が付いていない良さがあったのかもしれません。
野中 私も、もちろん集英社のことは知っていましたし、ちょうど小学生の頃に『週刊少年ジャンプ』が創刊されたこともあって親しみのある会社でした。それから、これは竹内とは違うかもしれないけど、普通のサラリーマンをやりたくないという気持ちが強かったんです。だから、夜遅くまで働いてもいいからネクタイをしないで会社に行って、自由に仕事をする編集者という仕事に就きたかったんです。
— それで実際に配属されたのは?
野中 入社した時は全員編集者志望でしたが、残念ながら私は、当時の名称で業務部という、営業部門に配属されました。その後一度編集部に異動になったんですが、それ以降はずっと販売部です。コミックス販売と書籍販売の両方に携わりまして、合わせると26年くらいになるのでキャリアの大部分は販売ということになります。
— これまでのキャリアの中でいちばん印象に残っている出来事は何ですか?
野中 コミックス販売にいた2011年頃、『ワンピース』が爆発的に売れて、総部数が2億冊を突破し、途中の巻の初版が400万部に達した時でしょうか。400万部をつくる製本工場を見に行ったんですが、機械をフル稼働しても全てつくるのに一週間くらいかかるんです。出来た本をそのまま置いておくと身動きがとれなくなるので、出来た端からどんどんトラックに乗せて出荷していく。それを見た時、こんなことはもう二度とないだろうなと思いましたが、本当になさそうなのでちょっと寂しいですね(笑)。
— 『週刊宝石』もかなり売れましたよね?
竹内 当時はすごく売れましたね。ライバル誌の中でいざトップをうかがうという所までいった辺りで、当然、会社としてはそこから派生した新たな媒体を考えます。そこで挙がったのが、写真週刊誌とマンガ雑誌でした。実はうちも元々はマンガに力を入れていた出版社だったんです。『鉄腕アトム』や『鉄人28号』などの人気マンガを連載していた『少年』、そして『少女』というマンガ雑誌を出していた頃はかなり売り上げも良かったんですが、しばらくして当時の社長が「これからは子ども向けの雑誌はつくらない」という大方向転換をして、まさに『ジャンプ』と入れ替わるようにしてマンガ雑誌から撤退しました。
ただ、集英社さん、講談社さん、小学館さんという御三家の景気の良さを見るにつけ、やはりマンガをやらねばなるまいという話になり、『週刊宝石』の増刊として大人向けのマンガ雑誌を出すことになります。僕はそちらに移って、8年くらい、潰れるまで関わりました。マンガ雑誌の編集者をやるのは初めてでしたが、やはり御三家の編集者とは総合力が違うのでとても歯が立たない。これはダメだなということで8年で潰したんですが、今の集英社さんと光文社の差は、完全にマンガでつきました(笑)。
野中 いや、今でも女性誌は光文社さんのほうが強いですから。
竹内 その後、僕は文芸誌の『小説宝石』に移り、最終的に編集長までやって、今は校閲部に移った、と。
— 竹内さんのこれまでのキャリアの中で最も充実していたのは?
竹内 やはり、入社直後の『週刊宝石』時代の現場ですね。文芸誌に移ると、今度は日本で存命の作家のほぼすべてとおつきあいすることになります。知の結集のような方々と身近につきあえたことも大きな財産です。

急速に変化する出版界の中で
— そんな中、仕事をする上で最も大切にしてきたことは何ですか?
竹内 ずっと編集に携わってきましたが、大切なのは人づきあいなんです。ようするに、取材相手や作家に好かれるかどうか。少なくとも人に嫌われないことが重要です。とはいえ、僕は根がルーズなので、それで出入り禁止になったこともありますが(笑)、そういうことはあまり気にせず、気に入ってもらえるまでとことん粘ることですかね。
— 作家の中には気難しい方もいると思いますが、気に入られるコツはあるのでしょうか?
竹内 僕は変に度胸があるというか、その作家の書いたものをあまり読まずに会いに行ったりするんです。だから、最初はなるべく仕事の話にもっていかずに、今でいう「雑談力」のようなもので相手の関心を引きつける。もちろん、最終的には、いつまでにどんなものを書いてくださいという話にもっていくわけですが、まず相手と仲良くなることのほうが大事で、仕事の話はその先にあるという感じでした。だから、いったん気に入られると長いおつきあいになりますね。
— 84年の入社ということは、ちょうど日本経済がバブルに突き進んでいく時代ですが、バブルの絶頂期あるいは崩壊後の影響はあったのでしょうか?
野中 数字だけで言うと、バブルが弾けて4~5年くらい経ってから、うちの業界の衰退が始まっているんです。今、前年を超えられない状態が17年くらい続いているんですが、金額ベースで見ると影響が出始めたのは1998年頃からですね。
竹内 ただ、今の出版不況とバブル崩壊はまた別のベクトルでしょうね。良くも悪くもバブルの影響はあまり受けていないんじゃないかな。
野中 そうかもしれない。バブルになって本が急激に売れたということもなかったですね。
竹内 今はそんなことは言われないですけど、僕らが入社した頃は、「不況になると本が売れる」と言われていました。ようするにお金をあまり使えないから本でも読もうか、雑誌で暇つぶししようか、と。そういう意味でも、バブル後の不況で売り上げが伸びたという印象もなかったですね。
— 今お話しに出た出版不況はやはり深刻ですか?
野中 私の個人的な感覚では、すごく落ちてきたのはここ1年です。消費税が増税してから雑誌も書籍もコミックスも全部落ちています。しかも落ち方が前にも増して激しくなっているのでかなり危機感を感じていますね。具体的にいちばん落ちているのは文芸小説の単行本で、毎年10%ずつくらい落ちている。このままいくと小説を買う人がいなくなるんじゃないかと心配ですね。雑誌は特に若い人向けが非常に厳しいですね。コミック誌も部数が減っています。少子化ということもあるし、一方で小説を買ってくれていた層もだいぶ歳をとられて本を買わなくなってきているのかなという気もします。
— ネットの影響も大きいのでしょうか?
野中 もちろん影響あると思います。うちも電子書籍でのコミックス販売は毎年過去最高の売り上げを更新しています。コミックスに関しては、リアルと電子を足すとまだ前年を上回っていると言えるんですが、雑誌は年々マイナスになってしまっているので、厳しい状況です。雑誌も電子で扱っていますが、金額ベースで採算ラインに乗せるのはかなり難しいと思います。
— そうした現状を突破する策はあるのでしょうか?
野中 各社いろいろ打開策を考えていますが、どれが答えかというのはすぐには見つからないでしょうね。
竹内 うちの場合、週刊誌『女性自身』以外にも『JJ』『CLASSY.』『VERY』『STORY』『Mart』等のラインナップの女性誌がメインということもあり、頼りになるのは圧倒的に広告収入です。その一方で、雑誌が独自に洋服や雑貨などをメーカーとコラボしてオリジナル商品をつくる動きも活発化しています。そういう意味では従来の出版社という形から、少しずつ別の分野とも連動していく動きが出始めていますね。
野中 昔は単行本も3年くらい時間をかけて売っていこうとしていましたが、今は文庫化までだいたい2年位です。かなり売れた単行本でも早めに文庫にするので、非常に勝負が早くなっています。単純に単行本が売れないので、倉庫にストックしていてもしょうがないから早めに文庫にしようという話になる。先ほど『ワンピース』の初版が400万部という話をしましたが、初版4000部という単行本はざらにあります。それだと最初から赤字に近いので、早く文庫にしてなんとかペイ出来ればいいねということになるんです。

卒業生が情報交換出来る場を
— ところで、お2人にとって、情報学部で学んだことは今のお仕事に活きていると思いますか?
竹内 僕は大学で勉強してきたことがほぼストレートに活きていると思いますね。国際報道のゼミに入っていたんですが、担当の教授はついその前まで朝日新聞の論説委員をやっていた一線級のジャーナリストです。とても温厚な方で、僕にとっては親父みたいな存在でした。他の先生方からも、皆さんがそれぞれの現場で得たことを直接聞くことが出来た。僕にとって、メディア人としての考え方やスタンス、編集者としての骨格はその4年間で完成したと言っていいと思います。
もう一つは、テレビやラジオ、新聞の仕事に関して一通り学ぶことが出来たこと。それによって、出版の仕事をするようになってから、テレビの切り口や新聞のアプローチなどを自分の仕事の仕方に加えることが出来ました。たとえば、法学部や文学部を出て出版社に入った人間の場合、それは出来ないわけです。意外とみんな、他の分野のマスコミの仕事の仕方や姿勢について知らないんですよ。大学時代にそれが一通り学べたことで、いろいろな角度からものを見られるようになったことは大きかったですね。
野中 素晴らしい答えですね。そのままお借りしたいくらい(笑)。逆に私は反省点として、もっと読書をしておけば良かったという後悔があります。自分の好きな動物ものや戦記ものは読んでいたんですが、純文学系を読んでいなかったので、入社してから他の誰よりも読書量が足りないことを思い知らされましたね。販売に配属されてからは、どの出版社のものでも、少なくともベストセラーと呼ばれるものは必ず読むようにしました。そして、少しでもいい所があれば、どこがどういいのかを分析するようになりましたね。
竹内 でも、僕もいわゆる純文学とかマンガは、学生時代にはほとんど読んでなかったですよ。根っからのジャーナリズム志向だったので、どちらかというと嫌いだった。ところが、仕事としてやってきたのは皮肉なことにマンガと文芸ですからね(笑)。もっとも、そこが評価された部分でもあるんです。「先生の本、全部読みました」というタイプではないので、どこかドライに見ているところがあった。見方が普通の編集者と違うわけです。それがかえって良かったんじゃないかとは思いますね。
— お2人は卒業後もお会いになる機会はあったんですか?
竹内 30年で2、3回じゃないですか。
野中 同窓会で会うくらいでしたね。
— 今回、竹内さんが音頭をとって文教大学ビジネス同友会を起ち上げられたそうですね。
竹内 実は20代の頃から構想はあって、同じ業界にいる人間が情報交換出来る場があるといいねという話は野中にもしていたんです。ただ、さすがにみんな忙しい時期だったので実現出来ずにいたんですが、50歳を過ぎてそろそろ暇になって来たので、ここら辺でやらないと「やるやる詐欺」になってしまうな、と(笑)。
— 具体的にはどんなことをやっていく予定なんですか?
竹内 現在加入してくれているのは150名くらいですが、民間企業や公務員、マスメディアそして起業自営者ほか、様々な職種で活躍しています。20代から50代まで、短大を含めた全学部の卒業生に亘るんですよ。OBであれば誰でも参加できます。次々とイベントを企画するなりして、その人たちを飽きさせない仕掛けをつくらなければいけないと思っています。
— 単なる同窓会ではないわけですよね?
竹内 もちろんそうです。僕の勝手なイメージでは、我々もあと数年で定年退職を迎えるので、たとえば定年後の再就職支援のようなものが出来ないかとか、あるいは後輩の中にはフリーで仕事をしている人間も多いので、お互いに仕事をシェアしたり協力し合っていける仕組みがつくれないかとか、いろいろアイデアはあるんです。時々集まって飲みながら名刺交換をするだけでも随分違うんですが、もう少しいろいろと仕掛けていきたい。たとえば、野中に書籍のマーケットについて話してもらうとか、いろいろと腹案はあるんですけどね。
— 20代の頃に集まるのとでは皆さんの蓄積も違うでしょうから、充実した会になりそうですね。
竹内 そうなんです。みんな苦労して大物になったなあと思いますよ(笑)。まずは2017年の創立90周年をひとつの目標に、少しずつ形にしていけたらと思っています。
— 楽しみにしています。本日はお忙しいところありがとうございました。
(2015年5月27日に対談実施)